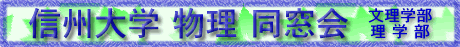
■ 春寂寥 (寺尾先生の“最終授業”に出席して)
來田 歩(理学22S 物性研究室) 30MAR.2008
【株式会社東海ゴム工業要素技術研究所 主担当員】
2008年3月8日に「寺尾洌教授(物性理論研究室)退職記念講演会」が開かれ、これに出席された來田さんにレポートと写真をお願いしました。來田さんからはこのようにインパクトのある印象を綴っていただきました。筆者・來田さんの要望もあり、事前に寺尾先生と講師の勝木先生にも目を通してもらったところ、勝木先生からは長文のご感想メールを、また、寺尾先生からも短文の感想をいただきました。來田さんのレポートのあとに、両先生からのメールもご紹介します。老いても(失礼)、学究へのあくなき情熱、緻密な探究と理路整然とした論理の構築方法は若々しく大いに学ぶものがあります。來田文への解説となると同時に、本学がおかれている今日的な背景の理解にも役立つでしょう。とにかく、寺尾先生、おつかれさまでした。(文中(※)マークは勝木先生ご指摘の部分です)* * * * * * * * * * * * * *「気がついてみると、自分が、信州松本を、ノーベル文学賞作家の著作のタイトルをもじって「懐かしい時の場所」と名づけて、何度となく足を運んでいた。
プライベートの松本行きは、さておき、辻村先生・鷺坂先生・宮地先生の退官記念、森先生の退官記念、信州大学と名古屋大学の共同の「インバー問題の発表会」、安達先生の退官記念、勝木先生の退官記念、吉江先生の退官記念、そして、内輪で行われた、天児先生の教授就任祝い。そのたびに、「寂寥」は「つのる」ようだった(なんだかんだいって、ほぼ皆勤賞じゃないだろうか、頼まれてもいないのに・・・)。
最近、行われた内輪での「天児先生の教授就任祝い」は、「銀嶺祭」の時期だった。
「銀嶺祭」といえば「メソン」である。
(※1)猪瀬直樹氏(たぶん「全共闘」)たちが、学内で暴れていた頃、理学部学生(たぶん、「民青」)は、教師側に立ち、乱暴狼藉ものを撃退したという、その関係で、理学部だけは、学園祭期間中、午後10時まで校舎内で居酒屋を開くことが出来た(と先輩から聞かされたような気がする)。代々3年生が、「それ」を担当した。
繰り返しになるが「メソン」である。
2年生は「物理の散歩道」という、物理に関して、なにか興味を持ったことを、とことんやって、発表する場を与えられた。もちろん、「物理の散歩道」は、寺田寅彦先生の随筆集を正しく継いだ近角聡信先生ら、ロゲルリストという集団からなる「物理大好き本」のタイトルからとっていた、と、わざわざ書かないといけないのは、最近の物理の学生は、そのことすら知らないという驚愕の事実に接したため繰り返しになるが、卒業後も、学園祭の時期は、懐かしくなり立ち寄った。
酔っ払いの吉江先生や、はぶりのいい永井先生や、理論物理の夢を語っていた故寺沢先生がいた。示し合わせているわけでもないのに、先輩、後輩が集まった。
その「メソン」がなくなっていた。校舎は新しくなっていた。もう、「懐かしい時」だけになってしまった、場所は、なくなった。頼まれもしないのに、駆けつけた退官記念のイベントも、寺尾先生で最後になるのかな、たぶん。
さて、その寺尾先生の退官記念のイベント・・・。
新しい校舎で、場所がわからず、少し遅れて会場に入っていくと、勝木先生が、前座をつとめていた。目があった。(※2)名古屋大学工学部応用物理学科の清水研究室(確か)から、新進気鋭の理論家が、信大教授に抜擢される。(※3)大阪大学基礎工の永宮スクールの金森順一郎が彼の視野にあった。計算機の能力では、一地方大学では、太刀打ちできない。そこで、(※4)地方大学は、ゼロに近いのだから、ゼロでもともと、ゼロに較べれば、プラスはプラスと、新しい分野に挑戦する。
「物性物理学史」。歴史なんて定年になってからやればよいといわれたが、学問は、老後の余技ではないとわかった、という。
最近になって本多スクールの(※)「曽根武」の評伝をものにした(※)(絶賛発売中です)。
そして、(※5)僕が学生の頃、受けた「物理学概論」でのエントロピーの授業。「資源物理学」と成った。槌田敦先生の定義した問題が、まったく評価されなかったことが、契機となる。
S=kLogWで微視的な熱力学、エントロピーを理解したとはいえない。(※)今でも、エントロピーがわからないと勝木先生は言う。物質とエネルギーの拡散は結びついている。エントロピーが温度差のところに落っこちていくと表現していた。熱機関と水車の論理体系は結びついていると僕の名古屋大学・安達研の先輩河宮さんを評する。勝木先生は、カルノーを再評価しているらしい。環境の多重構造から、エントロピー的な環境論に発展する(こちらも、絶賛発売中)。
アルバート・アインシュタイン、バーランド・ラッセルの共同声明の無視について、一言する。勝木先生は、健在である。その勝木先生が、同じ研究室の将来有望な学生を、信州松本に、ひっぱっていく。それが、寺尾先生であった。ということで、やっと、寺尾先生の最終講義である。
1960年代「インバー問題」で、勝木先生と矢継ぎ早に3つの論文を書いた。その研究が、 1990年代、ドイツで、また花開く。ワッサーマンやアチェトに、インバー問題のプロフェッショナルと紹介された。
Laves相構造金属化合物として、永井先生が自発体積磁歪5%というYMn2に出会う。リカージョン法で立ち向かう。大きな自発体積磁歪を説明できたという。
僕の知っている寺尾先生は、「物理演習」の寺尾先生である。ガリ版で刷られた青焼きのプリントの問題を選んで、黒板に書く。僕は、相互作用が距離の3乗に反比例する場合どうなるかという問題を、ランダウの「力学」に載っていた方法で解いた。曲座標変換して。距離は、原点に収束していく、角度は∞に発散していく。さながら、ブラックホールのように・・。高速で自転する。こんなんでいいのかな?
と思ったけど、こんなんでよかった。目をつけられた学生は怒鳴られ続けた。
最終講義では、「怒ることの感情表現しかしらない」と笑いをとる。
僕が卒業した後は、沖縄の学会や、ローマの学会で、寺尾先生と会った。
たぶんその頃、スピンフラストレーションの問題に取り組んだらしい。寺尾先生が指導した学生の名前と卒研、修論のタイトルを羅列して、説明していく。そんな中、2002年に「スピンJahn-Teller効果のエレガントな論文に出会い、正多面体の高スピンフラストレーションの研究に拍車がかかる。群論が出てくる。冗談を交えながらの講義も、俄然、数式ばかりになって、物理大好きの寺尾先生本領発揮である。本当に、この人は、物理が好きなんだなあ・・・。
印象的な聡明な女子学生の名前、本田育美さんと森崎梨恵子さんの名前が告げられ(会場にいたらしい)、共著で、(※)勝木先生とかつて「インバー問題」で矢継ぎ早に3本の論文を発表した熱狂を髣髴させる、再び3本の論文を書いたという。
摂動ハルミトニアンから、V-スピネル、量子歪み。まだまだ、研究は続く。実家の桑名に戻り、名城大学と大同大学の非常勤講師を務めるという。
《上記來田氏の原稿に対して勝木先生からいただいたメールをご紹介します(なお、5月17日付で先生から「補筆」を受け取り、追加させていただきました)》高藤様 新戦時06(2008)/04/24
勝木渥
拝復
来田さんの記事拝見。一読しました。異議申し立てをしたい個所が何ヶ所かありますが、来田さんの印象を来田さんの責任でお書きになるのであれば、私がとやかくいうべき筋合いのものではあるまいとも思います。
ただ、この記事が事前に勝木のチェックを受けているということになってもまずいので、最小限ここにだけは異議申し立てをしておきたいという点だけを、いくつか列挙しておきます。
****************************************
(1)
《猪瀬直樹氏(たぶん「全共闘」)たちが、学内で暴れていた頃、理学部学生(たぶん、「民青」)は、教師側に立ち、乱暴狼藉ものを撃退したという、その関係で、理学部だけは、学園祭期間中、午後10時まで校舎内で居酒屋を開くことが出来た(と先輩から聞かされたような気がする)》
という表現に内包される、全共闘運動への評価に私は同意しません。全共闘運動は、社会と学問の関係に関する私の考えを、私がより深く深めて行く上での貴重な契機をもたらしました。また、上の記述は、史実についても、それを正しく記述したものにはなっていません。
(080517補筆)
「理学部学生(たぶん、「民青」)は、教師側に立ち、乱暴狼藉ものを撃退した」のではなくて、「理学部学生は、全共闘運動に共鳴して教養部占拠・本部占拠に加わる者、かれらを暴力学生・大学と学問の破壊者とみなして、理学部防衛のためのバリケードを教室の椅子や机を使って築く者、対立の圏外に位置して自らの在り方を思索する者、事態を中立的ないし傍観的に眺める者、等々、さまざま立場をとった」のでしたし、「乱暴狼藉ものを撃退した」ということは、もしこの言葉が「理学部占拠に押しかけた者どもを撃退した」ということを意味するとすれば、全共闘の学生たちが理学部に、理学部占拠のために押しかけるという事はありませんでした。理学部のバラック校舎と本部のバラックの建物の間の広い空き地をデモっていた全共闘学生が、理学部のバリケード防衛の学生たちに向かって聞こえよがしに「理学部占拠!」と叫んだことが一度だけありましたが。「理学部だけは、学園祭期間中、午後10時まで校舎内で居酒屋を開くことが出来た」のは、「その関係で」(=学生が「教師側に立ち、乱暴狼藉ものを撃退した」から)ではなくて、「学園祭期間中、午後10時まで校舎内で居酒屋を開くことが出来た」頃の理学部にあった相対的にリベラルな雰囲気(これが大学をアカデミックな研究機関たらしめる必要不可欠の条件です)によるものだと思います。 (080517補筆/ここまで)
(2)
《名古屋大学工学部応用物理学科の清水研究室(確か)から、新進気鋭の理論家が、信大教授に抜擢される》は、私の信大就任の経緯について、正しくない印象を与えます。信大理学部物理学科の物性物理学科目の教授候補の話が来た時、私は志水(清水ではない)研の助手でした。新進気鋭の理論家ではなく、やっと最近になって集団電子模型での電子比熱と磁化率の計算を、名大に導入されたばかりの電子計算機を使ってやって、ようやくいくつかの論文を書き始めたばかりの、あまりパッとしない、駆け出しの研究者に過ぎませんでした。
私のところに信大物理の物性の教授の話が来たのは、その頃、大学における工学部の大拡張、企業における中央研究所ブーム、等々があって、物性研究者は「引く手あまた」で、新たに地方大学に文理改組で理学部ができ、物理学科がおかれて物性関係の学科目をおこうとしたとき、人材は払底していて、かつ設置のためにはマル合教授が必要であり、いわば窮余の一策だったのではないかと、私は推定しています。私は、信大教授の話をはじめて聴いた時、私に相応しいポストはたかだか助教授であって、教授などというのは、私には分不相応に高すぎる、と思いました。
(3)
それに続く《大阪大学基礎工の永宮スクールの金森順一郎が彼の視野にあった。計算機の能力では、一地方大学では、太刀打ちできない。そこで、地方大学は、ゼロに近いのだから、ゼロでもともと、ゼロに較べれば、プラスはプラスと、新しい分野に挑戦する。「物性物理学史」》という部分も不正確です。
(3-1)
前半部分:私の視野には、金森は入っておりませんでした(なお、金森は阪大理学部の永宮スクールですが、永宮の基礎工への転出後も理学部に留まりました)。私は志水研時代に展開した集団電子模型による磁性の研究の中で、強磁性発現のストーナー条件を満たさない場合でも強磁性が現われる可能性があるということを見つけ、これが fcc Fe-Ni 合金系におけるインバー組成近傍 での自発磁化の急落の理論的な説明を与えうるかも知れない、インバー合金の特性の理論的研究をこれからの自分の研究テーマにしようとの思いを抱いて信大に赴任しました。
そして、これまでよりも研究条件の悪い所での研究になるから、共同利用研を積極的に利用してやろう、自分が研究会を提案すれば、研究会に必ず出席できると思って、当時物性研の近角研の助教授だった石川さんに、一緒にインバー研究会を提案しませんかと打診したら、ちょうど京大の中村さんと物性研の近角さんとの間で同じ計画が進行していたらしく、中村・近角・石川・勝木の4人連名で提案がなされ、1968年月6月6-7日に研究会が開かれました。私はそこで「Invar 効果についての解説(理論)」と題する30分のレビューをしま した。
金森はこの研究会に参加しており、のちに長谷川と連名で、(自発磁化急落についてのわれわれの研究が分子場近似に基づいていたのに対し、近似の良さを一段高めた)CPA近似を用いた理論を発表しました。
さらにわれわれは、同じく分子場近似で、集団電子模型での磁気体積効果の理論を作り、それに基づく計算をやって、インバー合金の特性を論じました。それが来田さんのいう《(寺尾さんが)勝木と(共著で)かつて「インバー問題」で矢継ぎ早に3本の論文を発表した》という、その研究です。
論文はJPSJに1968年12月、1969年1月、3月に投稿され、それぞれ1969年5月、8月、10月号に掲載されました。第1報は簡単な物理学的直観に基づく考察によって、状態密度の形と自発体積磁歪との関係を論じたもので、私の寄与が相対的に大きかったと思いますが(私が第1著者になっています)、それをさらにきちんと定式化したのが第2報で、これはもっぱら寺尾さんの寄与によるものです(寺尾さんが第1著者になっています)。実は第4報も出ていて、これは1974年1月に投稿され、同年9月号に掲載されました。
(3-2)
後半部分:来田さんの表現では、金森と競争しても勝ち目はないから、物理学史に転進したと読み取られる可能性を含んでいますが、私はむしろ積極的に「日本物性物理学史の実証的研究」を私のライフワークとして選び取ったのです。
物性研でのインバー研究会での私の報告は好評でした。その頃、本多生誕100年を記念して本多記念会の『(欧文)シリーズ「物質科学」』 の出版計画が進行中でしたが、その中の1冊に『イン バー合金の物理と応用』というのがありました。物性研での研究会の直後、私にその本の編集委員会に委員として加わるようにとの誘いがあって、私はそれを引き受けました。その編集作業の中で、すでに戦前、本多光太郎や本多スクールがインバー研究を大々的に進めており、特に増本量(はかる)が超インバーや不銹インバーという新材料を開発していたこと、その研究の中でインバー特性の発現と磁性とを関連づける理論的考察さえなされていたこと等々を、初めて知りました。私がインバーの研究を始めたとき、まず取り上げたのは、イギリス・ソ連・アメリカの研究で、日本でインバーの研究がなされていたなどとは、想像さえしなかったのです。
そのとき私は、私が日本での研究をまったく知らぬまま、得々としてインバーの研究に取り組んでいたこと、日本における先人の仕事にまったく無知のままであったことを非常に恥ずかしいことだと痛切に感じました。そのことを反省して、本多と本多スクールの仕事を中心に「日本物性物理学史の実証的研究」に着手することにしたのです。その最初の論文は1973年に『物理学史研究』に掲載された「インバ−合金の研究と本多・増本」でした。
私はのちに、日本の物性物理学分野の長老たちから聞書きを取ることに精力的に取り組むようになりますが、その原点は、私が日本の物性物理学の歴史について無知であったことについての、恥ずかしさをともなう反省でした。
(なお、来田さんは《最近になって本多スクールの「曽根武」の評伝をものにした(絶賛発売中です)》と書いておられますが、「曽根武」ではなくて、正しくは「曽禰武」ですし、「ものにした」のはまず1995年3月付の科研費報告書であり、ついでその報告書に若干の補筆をして、雑誌 Boundary に掲載(断続的に連載)したのが 2001.11-2003.8、さ らにそれを大幅に増補して単行本にしたのが、2007年1月でした。
また、《絶賛発売中》などではなく、物理学会・信大物理同窓会・その他に持参したり、いろいろの人脈を辿ったりして、強引に押売りしているというのが実相です。アマゾンに一つだけ「絶賛」したカスタマーレビューが載っていますが、私の目にした書評はそれだけです。発売後1年経った今年1月末に新宿の紀伊国屋書店に行って、在庫を検索したら1冊あって、どの棚にあるという情報も書いてあったので、その棚まで行ってみたら見当たりません。付近の店員に聞いたら、棚を調べて「確かに見当たりませんねえ」といい、「ひょっとしたら」といって、その棚の下の大きな引き出しを開け、その中に押し込まれていた本の中から拙著を見つけ出してくれました。大きな本屋での拙著の扱いはこんなものです。)
物理学史に関する仕事では、私以外にも 17S の足助尚志さんが修士論文に基づいて書いた「茅誠司における Weiss理論の受容過程」(『日本の物理学者』東海大学出版会、 1995)があります。
(4)
来田さんが《地方大学は、ゼロに近いのだから、ゼロでもともと、ゼロに較べれば、プラスはプラスと新しい分野に挑戦》と書いていることにも、ちょっと説明が必要です。
(2)の冒頭に書いたような状況でありましたから、当時は、地方大学の新たに発足したばかりの物理教室に赴任しようなどという奇特な物性研究者はほとんどいませんでした。発足時の物性関係学科目の教授候補者・助教授候補者は予期しなかった事情が生じたり、もっと地理的条件のよい別の大学の新たなポストに着いたりして、着任しませんでした。
私はこのような状況では、物理学科に物性関係の研究室は出来ないかも知れないと、深刻な危機感を抱き、物性グループや物性小委員会に、日本における物性研究体制の構築や将来構想を論ずるさい、地方大学に研究基地を確立するということを視野に入れよ、地方大学の問題を地方大学だけの問題として知らぬ顔をするのではなく、日本全体の物性研究体制の一環として考慮に入れよと、執拗に声高に訴えることを始めました。そのことで少し目立ってしまったせいもあって、のちに人づてに、優れた業績を持つある物性理論家が「勝木は研究、研究といっているが、研究したかったら、地方大学に行ったりしてはだめだ」と言っていたと聞いたのです。
この言葉を聞いたとき、私はとても気が楽になりました。地方大学に行ったら、さっぱり研究しなくなった、などといわれることがないように、いくら条件が悪くても、やるだけの事はやるぞとかなり気負っていたその気負いが取れて、非常に気が楽になりました。外からの期待はゼロなのだ。やればその分だけプラスなのだと。
この事は、学生時代に私がある出来事から開いた悟り『物理の研究のみならず、概して研究というものは、だれかれに見せびらかすためのものではなくて、自分の心に起こった疑問を直視し、それへの納得できる答えを見いだそうとする努力なのだ』とあいまって、のちに私が私自身の強い関心のおもむくままに、オーソドックスな物理学とはやや異質な分野(物理学史や、エントロピー的生命環境理論)に踏み出そうとしたとき、それへのためらいをまったく感じさせませんでした。
なお、上にあげた「地方大学を研究基地として確立する」という考えは、多分私が初めて提起した考えだと思います。そのさい、坂田昌一の『科学に新しい風を』の中の「自国に根を下ろした科学を創る」という言葉から貴重な示唆を受けました。「自国」を「地方大学」と読み替えたのです。その頃、物性(理論)関係の共同利用研として基礎物理学研究所と物性研究所がありましたが、基研は、研究条件に(経済的にも雰囲気的にも)恵まれていない地方大学で苦闘している研究仲間の、研究のためのオアシスになる、ということを、基研の1つの機能として思い描いていたように思います。「地方大学を研究基地として確立することへの積極的な関与」というような考え方はまだありませんでした。
同時に私は、地方大学にいる物性物理学者と連絡を取り合い「地方大学懇談会(物性)」を立ち上げました。その第1回の会合は1968年4月に阪大豊中地区で開かれた物理学会第23回年会のときに開かれ、群馬大:滝沢・村上、鳥取大:山口、新潟大:横田、信州大:勝木の4大学5名が参加しました。以後、年会・分科会の度ごとに開かれて現在に至っています。第2回目以降は学会プログラムのIM欄に掲載されています。2回目は1968.10.5、東工大、参加者は5大学5名、3回目は1969.4.3、学習院大、参加者は6大学7人(ほかに京大理の若手が3人参加)という状況でした。
この「地大懇(物性)」は、活動内容を充実させつつ(最近「中小規模研究室懇談会(物性)」と改称しましたが)今なお活動を続けています。最近、物理学会に「研究費配分に関する教育研究環境検討委員会」という委員会ができましたが、この背後には、研究条件の改善に長年にわたって取り組んできた上記地大懇の活動の蓄積があります。いま香川大学教育学部にいる 4Sの礒田誠さんがこの委員会に名を連ねています。こんな形で物性研卒業生が関わっていることに、なんとなく満足感めいたものを感じています。
(5)
最後に《僕が学生の頃、受けた「物理学概論」でのエントロピーの授業……》という部分について。
これも記述に不正確さをともなっていますが、エントロピー学会誌『えんとろぴぃ』57号(2006.5)に「(自分史) エントロピー的生命環境理論の形成過程 ― 動機・着想・認識の展開と 深化」と題する報告を寄稿し、掲載されていますので、興味のある方はそちらをご参照下さい。
また《今でもエントロピーがわからないと勝木先生は言う》とありますが、実はエントロピー的生命環境論構築の過程で、私は熱力学レベルでのエントロピーがどういうものであるかを、よく理解しえたと思うにいたりました。この方面のことに関しては、近く発行される『物理教育通信』No.132 に「熱とエントロピー」と題するエッセイを寄稿し、掲載される予定ですので、興味のある方はそちらを参照して下さい(場合によっては、No.133 に掲載されることになるかも知れません)。
****************************************
たいそう長々と書いてしまいましたが、来田さんの文章に手を加える事はすべきではないと思いましたので、それとは別に、私のコメントを書きました。併載していただけると幸甚です。
来田さんは《勝木が前座をつとめていた》と書いていますが、時間配分が勝木90分、寺尾60分であることからも推定されるように、前半のトリが勝木、後半のトリが寺尾なのです。寺尾さんと安江さんの退職で、草創期のメンバーが全員消えることになりますので、寺尾さんの定年退職に便乗して、いまや私しか知らないであろう物性理論研究室の歴史を、できるだけ正確に語り残しておきたいと思ったのです。
怱々敬具
《上記2通の原稿を踏まえて、寺尾先生から以下のメールをいただきました》
拝復
「論文はJPSJに1968年12月、1969年1月、3月に投稿され、それぞれ1969年5月、8月、10月号に掲載されました。第1報は簡単な物理学的直観に基づく考察によって、状態密度の形と自発体積磁歪との関係を論じたもので、私の寄与が相対的に大きかったと思いますが(私が第1著者になっています)、それをさらにきちんと定式化したのが第2報で、これはもっぱら寺尾さんの寄与によるものです(寺尾さんが第1著者になっています)。」
との件りは、感謝して拝読しましたが、私の寄与が過大に述べられております。蛇足かも知れませんが一言。
その前数行に触れられた、勝木先生の「強磁性発現のストーナー条件を満たさない場合でも強磁性が現われる可能性があるということを見つけ、これが fcc Fe-Ni 合金系におけるインバー組成近傍での自発磁化の急落の理論的な説明を与えうるかも知れない」
という着想.がその後の研究をほとんど決めてしまう重要なことでありました。
私はコツコツと計算しましたが着想の新規展開に至りませんでした。このパラダイムは、山田銹二さんのメタ磁性の研究にも脈々と受け継がれております。基礎研究においては、独創的な最初の着想が決定的に重要であり、尊重されなければならないと思います。
なお、強磁性の新しい発現機構の論文は
Phys. Letters 8 (1964) 7 "A note on the conditions of ferromagnetism by the band model" by M. Shimizu and A. Katsuki
で、1964年1月1日号です。著者の順序は当時の「助手」の地位を今日に伝えています(などと自由に言える時代になりました)。
草々
寺尾
《さらに、上記寺尾先生の原稿をご覧になった勝木先生から、以下の原稿が届きましたので、併せて追加してご紹介いたします》****************************************
(080517補筆)
寺尾さんのコメントにも、コメントを付けたいと思います。それは、私とボスの志水さんとの関係について、正しくない印象を与える可能性があると思うからです。
(寺尾コメントへの勝木コメント)
私がストーナー条件を満たさなくても自発磁化が現われる可能性があることに気付いた時、研究室のボスである志水さんはロンドン大学に1年間の予定で滞在中でした。私はそのことを志水さんに知らせましたが、志水さんはロンドンでそれを発展させた長い論文を書き、滞在先の同僚ウォルファースがそれに感心しました。志水さんは、その論文を発表する前に、寺尾さんがあげたレターを書いて、投稿したのです。ウォルファースはなぜそんなことをする必要があるのかといぶかったそうですが、こうしなければならない理由があるのだと説明したそうです。志水さんの帰国後、それと入れ替わりのように私がウォルファースのもとに留学しますが、私からインバーの話を聞いておもしろがったウォルファースは、ストーナー門下の昔の同僚、リーズ大学のローズと連名で、インバーの論文を書きました。
私が「ストーナー条件を満たさなくても自発磁化が現われる可能性」に気付いたのは、Niの磁化率と自発磁化の計算の過程であったのですが、磁化していないとしたときの磁化率が絶対0度から温度上昇とともに徐々に増大し、ある極大を経て減少に向かうのです。したがって、この磁化率の逆数(1/χ)は絶対零度でのある値から一旦減少し、極小値を経て再び増大することになります。もし分子場係数の値が、絶対0度での1/χより小さく(=ストーナー条件不成立)、極小値より大きかったとしたら、ストーナー条件を満たすある温度範囲でだけ磁化が現われるということになるかもしれない、こんな物質の存在を予言することになるかも、と期待しながら調べてみたら、絶対0度でも磁化している(つまりストーナー条件が満たされなくても自発磁化が現われる)ということになっていたのです。
こういう計算を私ができるようになっていたのは、都立大学助教授であった志水さんが新しくできた名大工学部の応物教室に赴任して来て、猫の手でも借りたいほどの状況であったときに、むかし名大理学部物性理論研(S研・有山研)で助手と学生の関係にあった私は、教養部物理の助手をしていましたが、志水さんに弟子入りして、状態密度が与えられた時にどのようにして磁化率や電子比熱の温度係数を計算するか、金属や合金の比熱の測定値からどのようにして格子比熱を差し引き、電子比熱を見積もるか、などを詳しく教えてもらったのです。そしてその頃、一連の金属合金の低温での比熱の測定データが次々と出てきていましたが、跳び跳びの組成の電子比熱のデータから、どのようにして状態密度を導き出すか、その技を、ひところ都立大学の志水さんのもとに内地留学してその頃は山梨大学にいた、S研2年先輩の高橋さんが手を取るようにして教えてくれました。これらのことを考えると、レターの著者の順序など、私にはどうでもいいことなのです。
やがてその歴史や著者の名前など遠い昔に忘れ去られて、ただその内容だけが人々の中に常識として広まっているという状況になっているなら、著者冥利に尽きるというべきでしょう。常識になってしまうと、それの適用限界が忘れられて、人々の知的創造力に対する天与の桎梏として機能する怖れなしとしませんが。

